原作『FF7』(FINAL FANTASY VII INTERNATIONAL、ファイナルファンタジー7 インターナショナル for PC)の感想&レビューです。

「仲間」がいないと-10点、ゲーム媒体ならではの体験重視、テンポや快適性が悪いと減点、ストーリーは採点対象外などのレビュー方針は以下のリンクより。
関連記事:ゲームレビューにおける方針まとめ
1.概要
1997年にPSで発売された『FF7インターナショナル』のPC版。スクエニ公式ストアでDL販売。
現行他機種と同様に高解像度対応、多言語対応、公式チートなどが実装されている。
今なお最高傑作と名高い世界観・ストーリー・キャラクターに加え、2Dドット絵からフル3Dになった壮大なワールドマップ、マテリアシステムによる奥深いカスタマイズが特徴。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2013/5/16 | 国内PC版 |
| ハード | PCスマホなど全機種 | |
| 外部ストア | indiegala | 日本語なしのSteam版 |
| メタスコア ユーザースコア | 81 8.9 | Switch版 |
| オープンスコア | 81 | |
| Steamレビュー | 92%非常に好評 | |
| Amaonレビュー | 3.8 | Switch版 |
| ゲームカタログ | 良作 | |
| 平均クリア時間 | 49.5時間 | |
| ストーリーを教えて貰うwiki | ここ | |
| スタッフロール(クレジット)人数 | 407人 |
2.購入価格やプレイ記録
2020年のPS4版『FF7R』発売時にミッドガルのみの一本道であることに失望してしまい、代わりに原作をMOD導入してプレイしようと50%オフ787円で購入していた。
しかし、日本語環境でのMOD構築が困難であったためそのまま積んでしまい、PC版『FF7リバース』が出る前の2024年7~8月にかけて英語環境でMOD構築して約50時間でクリアした。(プレイ中の英語への翻訳時間やMOD原因のクラッシュ巻き戻し時間含む)
なお、原作『FF7』は2,3周クリアした記憶はあるものの、『FF7インターナショナル』は今回のPC版が初見プレイ。
コンピレーション作品についてはBCを除くAC/ACC/CC/DC/LOは視聴&クリア済み、スマホ向け『FF7EC』もプレイ中。
また、以下の記事にまとめている大量のMODを導入しており、グラフィック向上はもちろん、英語フルボイス化、システム改良やセーブエディタによるセフィロス加入なども行っているため、MODなしバニラゲームに対するレビューとは異なる。
関連記事:PC版原作『FF7』究極のMOD環境構築
3.レビュー
トップクラスに魅力溢れる世界観・ストーリー・キャラクター
現代的な機械文明に剣と魔法のファンタジーが融合した舞台は『FF』シリーズでもよく採用されていて今となってはそこまで珍しいものではない。しかし、これに加えて本作の魔晄エネルギー=魔力の源=精神/魂の集合体という根幹の設定がストーリーにもキャラクターにもシステムにも深く絡みあって説得力のある魅力的な世界観となっている。
ストーリーについては主人公の正体が〇〇、追い続けたラスボスの正体が〇〇など進行に応じて明かされる事実に対する伏線が巧妙に仕込まれており、全体を知った状態でプレイしても楽しめるほど非常に良く出来ている。
しかも、驚くほどテンポがよく、ミッドガルは6時間、DISC1は20時間ほどしかかからない。バレットとダイン関連やヒュージマテリア争奪戦はいいイベントなのに、テンポがよすぎて今回プレイするまで忘れてしまっていた。
ちなみに、「主人公が実は〇〇と後半に明かされる構成」は同時期の『FF8/9/10』『ゼノギアス』でも採用されていていずれもシナリオ面で評価は高いので、やりつくした手法と思わず今後も積極的に採用した方がいい気がする。
大枠のストーリーそのものは動画で見ても同じ感想を得られるので採点対象外だが、本作はプレイヤーによって異なる体験が大量に用意されている。
有名な蜜蜂の館の女装イベント、デートイベントを筆頭に、無数の選択肢、編成中のキャラによって変わるイベントセリフ、さらにはDISC1の山場である忘らるる都までにチョコボ牧場、コンドルフォート、ゴンガガ、神羅屋敷、ウータイなどは立ち寄る必要すらない。
DISC2では短期間ティファとシドの操作パートがあり、その間にユフィやヴィンセントを仲間にしたりウータイイベントを消化することもでき、専用のセリフまで用意されている。ヒュージマテリア争奪戦においては4つ全て失敗することも可能でそれでもストーリーは進行していく。しかも失敗専用ムービーまで用意されている。(失敗するとマスターマテリアが取れなくなるという取り返しのつかない要素でもある)
DISC3では各キャラの掘り下げシナリオも用意されていて、現代でいう隠されたサブクエ状態なのでプレイヤーが自力で見つける必要がある。
今回やり直すまでシナリオは一本道の印象だったが、ここまでプレイヤーによって体験が変わる作りだったことに驚いた。
上記の世界観とストーリーゆえか、9人の仲間はもちろん、セフィロスを筆頭に、神羅幹部、タークスなど敵キャラも含めて全てのキャラクターが記憶に残る魅力的な人物となっている。人外キャラが二人も仲間にいるのもポイントが高い。
比較として『FF10』も世界観・ストーリー・キャラクターすべてが魅力的であるものの、『FF7』よりは仲間や敵キャラの魅力が一段劣っているイメージであり、なぜ『FF7』のキャラが魅力的なのか言語化するのは難しい。
アルティマニアなどのインタビューを読むと、昔の流れで担当者一人が街単位でセリフ含むイベントを作っていたこと(イベント間の繋がりに唐突感がある原因?)と、ボイス収録がないゆえに開発終盤までイベントを作り直せたことも原因の一端であると思われる。
また、フィールドでは3頭身であったため、オーバーリアクションでコミカルに描かれるシーンが多いことも魅力の向上に寄与している気がする。
今でも斬新なワールドマップ表現とレベルデザイン
この動画を見て欲しい。
MODによりグラフィック向上、描画距離向上、カメラ拡大縮小など実現しているもののそれ以外は原作のものである。
ワールドマップに水平線が存在し、昨今のオープンワールドですらほとんど実現していないシームレスな球体惑星風のワールドマップ表現がなされている。おそらく『FF8/9』『ゼノギアス』も同様の表現だったと記憶している。
実際は、ある地点からカメラを最大限引いて見える範囲がほぼ世界全体となっていて動きに応じてフィールドが繰り返し読み込まれており、惑星ではないのにそう思わせる表現を当時実現していたことに驚かされる。歩くこともできるワールドマップ上を飛空艇で飛び回る楽しさもあり、今でも同様の表現でやってほしいくらいの技術。
PS2の『FF10』からワールドマップがなくなってしまったことは非常に残念であり、その後、『FF零式』『DQ11』『聖剣ToM』などにはワールドマップがあるものの本作のような水平線はなく、端まで行くと反対側から丸ごとロードされる作りで『FF7』より劣った表現と感じてしまう。
レベルデザインとしても、徒歩とチョコボから始まり、バギーによる砂漠と浅い川、タイニーブロンコによる川と浅瀬、草原にしか降りれない飛空艇による空の移動、潜水艦による海底移動、山川海チョコボによる無制限移動と進行に応じて行ける範囲が広がっていく作りはやはりワクワクする。
終盤のチョコボでしか行けない場所に強力な装備やマテリアがしっかり配置されているのも探索のしがいがあり嬉しいポイント。
ワールドマップはなくとも自由に動ける広いフィールドがベースとして存在するのは大事であり、そういう面で『FF10』『FF13』『FF7R』のような一本道系は個人的に評価は低い。
PC版待ちの『FF7リバース』以降は『FF7』と同程度のレベルデザインになっていそうで期待している。
コマンドRPGとして史上最高と断言できる多彩で奥深いカスタマイズ
毎回世界観もシステムも変わるFFシリーズにおいて、本作で採用されたマテリアシステムの自由度と完成度が異次元のレベル。
おそらく『FF5』のジョブアビリティを自由に装備するようなイメージから発展したと想像できるマテリアシステムは、武器防具のマテリア穴に「魔法」や「コマンド」や「召喚獣」をセットすると戦闘中にそれが使えるようになるというもの。
普通はこれだけで十分なのだが、他のマテリアとペアにすることで効果を発揮する「支援マテリア」の存在がカスタマイズの幅を無限に広げている。
支援マテリアには「ぜんたいか」「ふいうち」「まほうみだれうち」「コマンドカウンター」など13種も存在し、単にこれらを仲間9人に適当にセットするだけでも無数の組み合わせがある。
さらに、原作『FF7』当時は知らなかった仕様として同じマテリアを複数セットすると複数の支援効果が得られる。
例えば、最強魔法「アルテマ」+「まほうみだれうち」、「アルテマ」+「MPきゅうしゅう」とすれば4連続アルテマでMP回復したり、「ものまね」+「コマンドカウンター」×2とすれば被弾時に2連続ものまねをする。
最強召喚「ナイツオブラウンド」+「ふいうち」、「ものまね」+「ふいうち」×9とすればバトル開始直後に召喚獣の10連続攻撃により最強の敵すら倒せてしまう。
難易度が無意味になってしまうほどぶっ壊れビルドが作れるので以降は採用されなかったと思えるほどカスタマイズが幅広く奥深い。とはいえ、これらのセットを実現するには膨大な稼ぎが必要でありのその労力に見合っていると思える。
APによりマテリアが成長すると同じマテリアが生成される(分裂する)という仕様も無限に遊べるやり込み要素として素晴らしい。
マテリアにより全キャラ最強にできてしまい個性がなくなってしまう対策として、本作から導入されたリミット技の存在も成長要素およびやり込み要素として上手く機能している。
現代においては『FFオリジン』などのハクスラジャンルでは同程度のビルドの幅広さを実現しているゲームはあるものの、コマンドRPGとしては当時はもちろん現在に至るまで史上最高と言える。
もちろん全てのコマンドRPGをプレイしてるわけはないが、プレイしてなくてもそう断言できるほど自由度と完成後が高すぎる。
UI、BGM、その他
27年も前のゲームなのにUIにおける不便が一切ない。
厳密には原作『FF7』ではマテリア整理ができずぐちゃぐちゃだった記憶があるが、『FF7インターナショナル』では全キャラのマテリアを一覧表示して付け替え&整理できる機能がありこれが非常に便利。
マテリア以外のメニューや戦闘中のコマンドはシンプルなので不便と感じることはなかった。

BGMは好みによるので数曲を除いて刺さらなかったが、それでも記憶に残る音楽ばかりであり植松氏の凄さは疑いようがない。
ここまで大絶賛してきたもののもちろん不満点はある。
MODで別次元に向上させてもグラフィック(特にキャラクター)の古さは否めないし、フィールドは基本的に見下ろしなど固定カメラなので奥行きがある場合は無駄に歩かされてる感覚でワールドマップ以外はイマイチだった。この辺りは『FF7リバース』以降に期待。
MODで全方位アナログ移動できるようにしていても、原作の4軸移動がベースになっているので思った方向に歩けないことも多々ある。
オンオフできるとはいえランダムエンカウント率も高く、雑魚戦でわざわざコマンド入力するのはめんどくさい作業で楽しくはない。同じ作業であっても動かす楽しさが常にあるアクションの方がやはり好み。なお、無敵のセフィロスを編成してフルオートで戦ってるときはそれでも楽しさは感じたので、『ドラクエ』の作戦(オート戦闘)のようなシステムがあればいいかもしれない。
編成した3人以外は経験値半分、AP0なのも育成時間の水増しに感じる。これはMODで控えにも入るようにした。
取り返しのつかない要素が多いことも現代においては減点である。
4.個人スコア
90点/100
※点数はレビュー方針に沿った感覚的なもの。70点あたりがSteamでおすすめするライン。
プレイ前は思い出補正が大きいと思っていたが今回プレイし直して改めて『FF7』の完成度の高さに驚かされた。
街とダンジョンのみ現代風の3人称視点にしてワールドマップ表現はこのままでもいいと言えるほど十分通用する。
史上最高のマテリアシステムはリメイク以外にも類似システムを採用してほしい。
なお、MODありきの点数であり、仮に現在バニラでプレイしたらグラフィックや戦闘テンポやユーザービリティの減点が大きくなり75点くらいになると思う。実際最もレビュー数の多いSwitch版のメタスコアは81となっている。とはいえ発売当時なら間違いなく満点の出来。
-2024/8/26



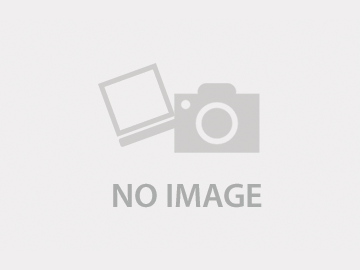

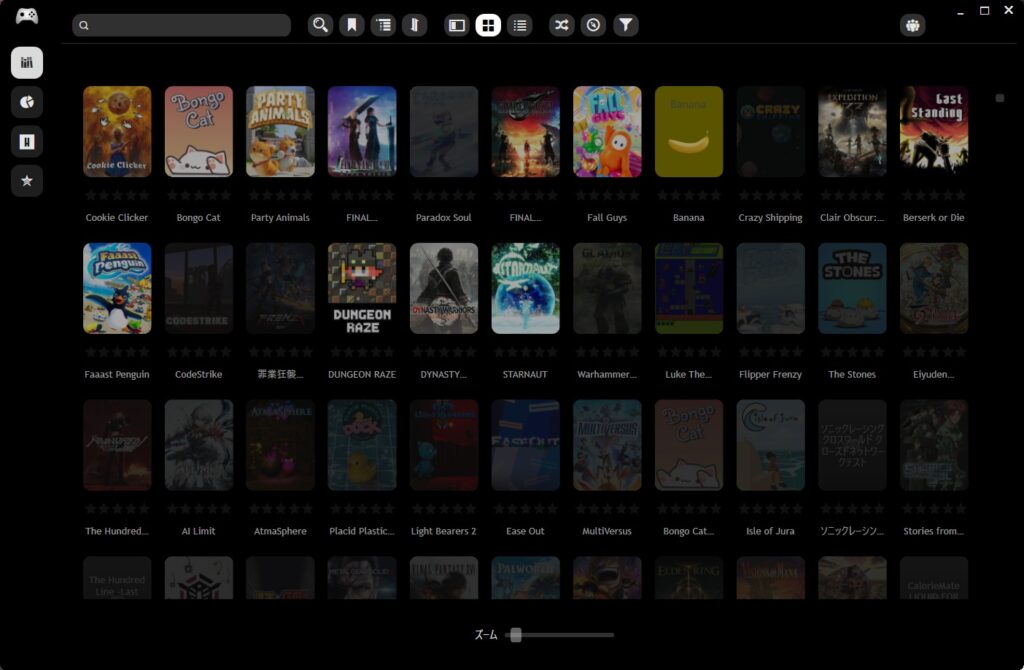





Steam版がMSストア同等版になって日本からも購入できるようになるのはほぼ間違…